
インド、デリバティブ市場の大躍進【下】
2025-12-12インドで個人投資家のデリバティブ取引が急増している。2024年の世界89デリバティブ取引所において、取引量トップはインド・ナショナル証券取引所(NSE)、次いでBSE(旧ボンベイ証券取引所)が続き、2023年に続きインドの取引所が1位、2位を占めた。コロナ禍の期間中に投資デビューした若年層が中心となり、NSEの個人保有比率は過去最高の18.2%に達した。スマホと電子認証でわずか数分で口座が開設でき、株価指数先物「Nifty50」などのオプション取引が爆発的に拡大した。だが規制当局の調査では個人の9割が損失を抱えるという。急成長する市場は韓国の90年代を想起させるが、インドでは加熱する投機熱に対し「統一契約ノート」導入など制度改革が進んでいる。
トマトの価格が政権支持率に、金融当局の理事も注視
インドでは近年、トマトや玉ねぎといった生鮮品の価格が乱高下を繰り返している。モンスーンの雨が農地を覆えば供給が減り、晴天が続けば一気に値崩れする。カレーの食材に欠かせないトマトや玉ねぎだが、実はこれらの価格動向は同国の金利政策に密接に関係している。
インド準備銀行(RBI)は、物価上昇率の目標を4%前後に据えているが、実際の消費者物価指数(CPI)では食品が約半分を占める。先進国で食品比率が2割前後にとどまるのに比べると突出して高い。トマト、玉ねぎ、豆類、穀物、乳製品など、これらの価格変動が家計を直撃しすぐに政権支持率にも跳ね返る。金融政策を決める理事たちは、毎月の農産物流通や市場価格を注視しながら利上げか据え置きかを議論している。
実際、過去数年のRBI会合の声明には「野菜価格の上昇」「豆類の供給逼迫」といった文言が並んでいる。2023年夏、トマト価格が一時1キロ当たり100ルピーを超えると、政府は輸出禁止や在庫放出で急場をしのいだ。トマトの強盗事件も発生し、運搬に警備会社を雇う業者もあった。RBIも「食品インフレが一時的か否かを見極める」として利下げを見送った。インフレ率が上限6%を超える局面では、トマト1個の値段が金融緩和の行方を左右する。
またインドでは玉ねぎの価格が3倍に跳ね上がった2019年、与党の支持率が急落し、政府は慌てて輸出禁止措置を発動した。トマトや玉ねぎの高騰は、選挙を左右する要因とまでいわれる。金融当局が利上げで物価を抑え込もうとしても、供給ショックが原因なら効果は限定的で、結局は財政措置や流通支援を併用せざるを得ない。
インドを含む新興国の多くは、こうした「食料主導型インフレ」に直面している。インドネシア、フィリピン、バングラデシュでも、CPIの40~60%が食品関連だ。国民の所得水準が低くエンゲル係数が高いため、野菜や穀物の価格上昇は国民生活に直結する。結果として新興国の中央銀行は、欧米のようにコアインフレ(除く食品・エネルギー)だけを見て政策を決めることができず、食料の価格動向に翻弄されている。
一方先進国では、こうした生鮮品の価格変動は一時的要因として扱われる。日本銀行や米連邦準備制度理事会(FRB)は、サービスや賃金の動きを重視する傾向にある。対して新興国では、マーケットより市場(バザール)のトマトが政策を動かす。金融政策が生活の実感と密接に結びついている点で、インドの中央銀行は極めて現実主義的な機関といえる。
近年は気候変動による収穫不安や物流混乱も加わり、食品インフレは一段と不安定化している。中央銀行が金利を上げれば企業投資が鈍り、据え置けば物価上昇が続く。金融政策と農業政策の狭間で、新興国の中銀は綱渡りを強いられている。
コロナ禍デビューの若年層が牽引、加熱ぶりに規制強化も
インドの金融市場に個人投資家の参加が激増している。これまで機関投資家や外国資本が主導してきた株式・デリバティブ市場だったが、インド・ナショナル証券取引所(NSE)の発表によると、個人投資家の株式保有比率は過去最高の18.2%に達し、うち直接保有分が9.8%ある。
背景には、スマートフォンとオンライン証券アプリの急速な普及がある。口座開設は指紋認証と電子KYC(本人確認)で数分しか要しない。2020年以降、爆発的に増加しているインドのデリバティブ取引量だが、これはコロナ禍を機に投資デビューした多くの若年層が、今では主力層に変わったからである。
2019年時点で29%にとどまっていた20~30代の投資家比率は、2023年には48%にまで跳ね上がった。2025年にはユニーク投資家数(口座の重複を除いた純粋な投資家人数)が8,000万人を突破し、全世帯の17%が株式を直接保有しているとされる。
こうした動きは地方都市にも波及している。これまで投資と無縁だった内陸州や農村部での新規口座開設が増加した。ミューチュアルファンド(日本でいう投資信託)の利用者も爆発的に増え、同分野ではリテール投資家が全口座の9割超(91.7%)を占めるまでになった。かつては限られた富裕層に限定されていた市場が、庶民の資産形成の場へと変貌した。
デリバティブ取引の中心にあるのは、株価指数を原資産とする「Nifty50」と「Bank Nifty」のオプション・先物取引である。NSEの株価オプションにおける2024年年間出来高は1,233億枚と、アメリカや中国をはるかに凌ぐ取引量を記録した。Nifty50はインドを代表する50社で構成される指数で、市場全体の動きを映すバロメーターとなる。一方、Bank Niftyは銀行株を中心に構成され、金利や金融政策の変化に敏感に反応する。これらはボラティリティが高く、短期売買に向いているため、個人投資家やアルゴ取引業者が集中している。 この2大指数に次いで取引が多いのが、インフォシスやリライアンス・インダストリーズなど大手企業株を対象とした個別株デリバティブである。
金融市場における急激な発展においては、全世界のあらゆる市場で必ず投資家のリスク認識が後手に回る。インド証券取引委員会(SEBI)の報告によれば、先物・オプション取引を行う個人投資家の約9割が損失を出しており、2024~25年度にはその損失額がさらに拡大した。リテールマネーの熱狂が、やがて社会問題に発展しかねないという懸念も出始めている。
フィリップキャピタル(インド)取締役のラジェンドラ・バムバーニ氏は本紙の取材に対し、「インドの株価オプションが急激に伸びたのは、商品の小口化が大きな要因」としながらも「あまりに国民の投機熱が加熱し過ぎたことで、今は規制強化の流れに入っている」と現状を述べた。
実際SEBIは取引所制度の透明化を進め、7月にNSEとBSEで「統一契約ノート」(Single Contract Note)を導入した。取引内容や手数料を共通書式で記録し、誤報告や不正を防ぐ狙いがある。さらに投資家教育プログラムの拡充やデリバティブ取引に関する警告制度の強化も進んでいる。
それでもインドの個人投資家熱は当面冷めそうになさそうだ。先述のトマト高騰問題にしても、トマトそのものは先物市場では取引されていないが、政府やSEBIに価格安定化のための市場整備を促し、農産物指数先物や青果バスケット型デリバティブの開発議論を後押ししている。トマトは鮮度が短く標準化が難しいため、現物市場が依然として価格形成の中心ではあるが、2023年の高騰時に政府備蓄の放出で急場を凌いだあたりは、日本における令和のコメ問題と酷似している。
インドのデリバ市場発展、韓国の「いつか来た道」
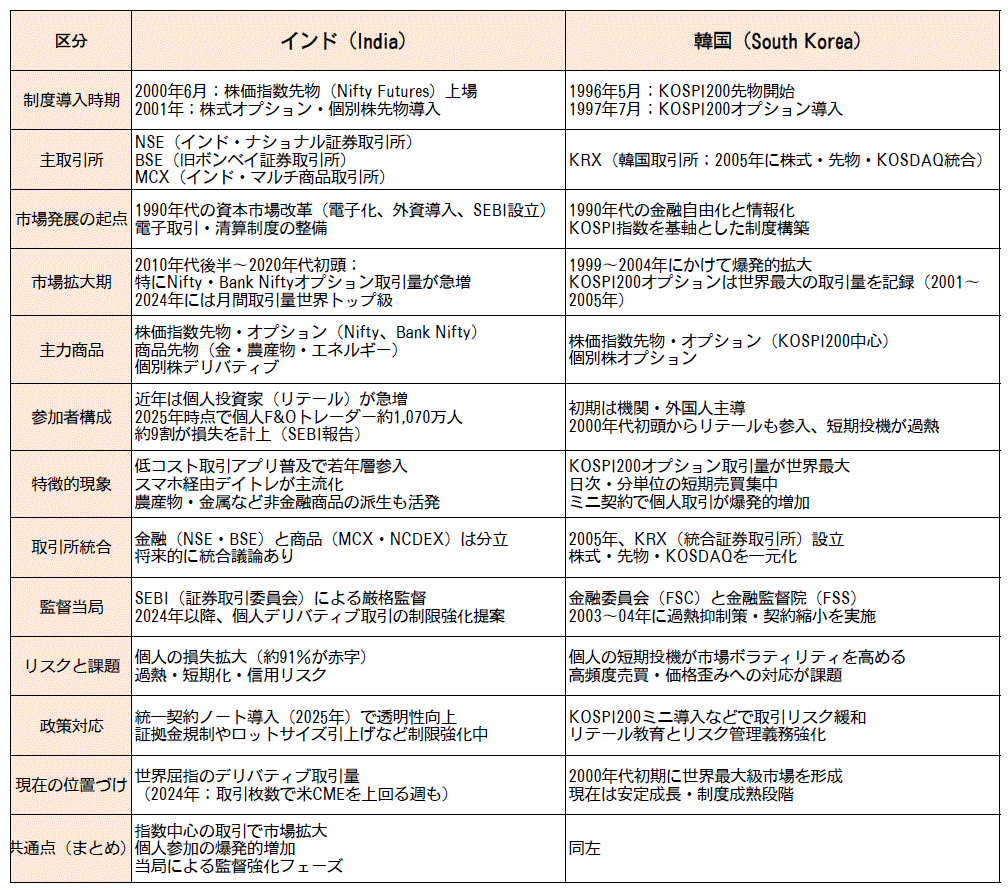
インドのデリバティブ発展プロセスは、1990年代の韓国を知る人間にとってはどこか既視感がある。当時の韓国は経済自由化とIT化を背景にKOSPI200先物・オプションを導入し、世界有数のデリバティブ大国へと変貌した。インドが2000年に株価指数先物を上場させた歩みは、ある意味で韓国の延長線上にある。NSEとBSEによる電子取引の普及、透明性の高い清算制度、投資家教育の推進が、市場拡大の原動力となった。つまり勢いの裏に「個人主導の短期投機ブーム」が勃興した点である。2025年時点で、インドでは推定1,000万人超の個人投資家がデリバティブ取引に参加しているが、2000年代初頭の韓国でも、KOSPI200オプションが「個人のカジノ市場」と呼ばれ、過熱抑制のための規制強化が行われた経緯がある。また、両国とも政府・監督当局が市場の透明化を推進している点も共通する。前述のようにインドでは統一契約ノート制度を導入し、全取引所で共通書式の報告を義務化した。これは韓国が2005年に取引所を統合して韓国取引所(KRX)を発足させたように、制度整備による信頼確保を図る姿勢と同様である(表参照)。
異なるのは、市場の裾野と多様性である。韓国が株価指数に集中したのに対し、インドは株式・金属・農産物・エネルギーと多層的な商品市場を抱える。さらに、人口ボーナスとスマートフォン経済を背景に、若年層がSIP(積立投資)やミューチュアルファンドと並行してデリバティブに参入している点もインド独自の現象である。インドのデリバティブ市場は今、韓国が20年前に経験した成長から安定への転換点に差し掛かっているといえるだろう。
参照表:インド・韓国比較表(Futures Tribune 2025年10月24日発行・第3392号掲載)
リンク
©2022 Keizai Express Corp.